一人ひとりが、
一人ひとりに、
できることを。
社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生
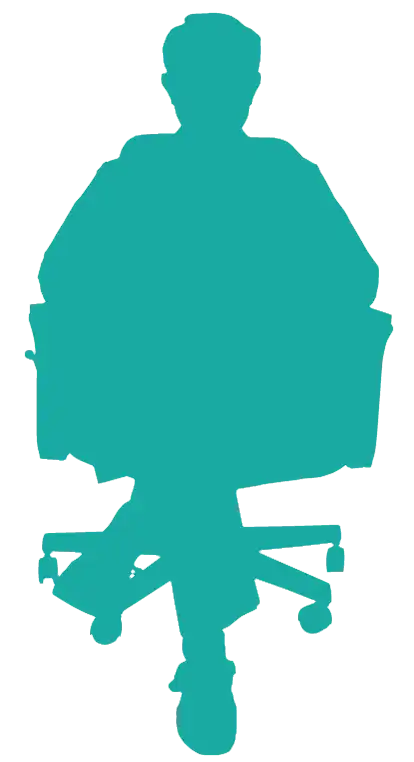
GREETING
やさしく、ひたむきに。
一人ひとりができる ほんとうの思い
1987年1月、札幌市に本院を開設して以来、当法人の理念は、院内に標示している4つの基本方針に集約されています。
人はそれぞれに価値観や人生観に違いがあります。
それは許容されるもので、そこに個性が生まれてきます。
しかしながら、ある目的に向かって行動をともにする時に忘れてはならないことがあります。
それは、人に対して思いやりを忘れてはならない、人に対する誠意を忘れてはならないということです。
患者様の思いに気づき、どのように受けとめているか。
そして、自分の心のなかに、その思いがほんとうにあるか。
私たち医療に向かう者として、人間的に一流のこころをもっていることが必要不可欠と考えます。
その一人ひとりの心に芽生える思いが信頼となり、質の高い医療へと導いてくれるからです。
そこからすばらしいものが生まれてくるのではないでしょうか。
皆様も気づかれたことがありましたら、お聞かせください。
これからも皆様のご支援・ご指導を賜りながら、職員一同、日々努力する所存です。
ひたむきに、やさしく。
これからもよろしくお願い申し上げます。

理事長 大橋 正實
HOSPITAL / CLINIC
施設紹介
PHILOSOPHY
法人理念
病院理念
- 私たちは専門病院として皆様に満足していただける医療を提供します。
基本方針
- 私たちは開かれた病院を目指します。
- 私たちはあたたかい手、やさしい目、感謝の心を持っています。
- 私たちは対話を大切にします。
- 私たちは質の高い病院を目指し、努力します。

当法人のロゴマーク
専門領域である耳・鼻・咽頭を
親しみやすくシンボル化しました。
やわらかい曲線は患者さんへの思いやり、
立ち上がる力強い直線は「治す」治療への
強い信念を意図しています。






